「民泊を始める際にはどんなことに気をつければ良いのかな?」
「自身が所有している空き家を民泊施設として使えるのか知りたい」
「民泊を始めたいけど近隣住民とのトラブルが心配」
民泊は、訪日外国人数が急増した2015年頃から普及した宿泊サービスです。2018年には「住宅民宿事業法(民泊新法)」が施行され、法令にのっとった宿泊サービスとして、一般的に利用されるようになりました。
民泊は、資産活用や宿泊需要に応えるサービスとして有効です。しかし、宿泊業に慣れていない他業種や個人が参入したことや、一般住宅を利用したサービスであることなどから様々な問題が指摘されています。
そこでこの記事では、これから民泊を始めてみたいと考えている方に向けて、以下の内容について解説します。
民泊運営を始める前に抑えておくべき情報を紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
民泊について30秒でサクッと解説
民泊とは、住宅すべてもしくは一部を利用して提供する宿泊サービスです。民泊は以下の3つの法律のいずれかに即して営業する必要があります。
民泊が普及する以前、宿泊サービスの提供は「旅館業法」に基づき、都道府県から営業許可を取ることが一般的でした。その後、旅館業法に基づいた宿泊専門の施設ではなく、自身が所有する住宅やアパートの1室を宿泊施設として提供するサービスが増加します。そのような状況下で、2018年6月に住宅民宿事業法(民泊新法)が施行されました。
また、国家戦略特区法は、国の成長戦略の実現に必要な規制改革が目的の法律です。国家戦略特区法に基づく民泊(特区民泊)は、法律で指定された地域においてのみ営業できます。
それぞれ法律は、宿泊サービスを行う建物や設備についての定めのほか、営業日数に関しての規制もあります。各法律の概要については、以下の表を参考にしてみてください。
| 住宅民宿事業法(民泊新法) | 旅館業法 | 国家戦略特区法(特区民泊) | |
| 申請方法 | 届出 | 許可 | 認定 |
| 営業日数制限 | 年間180日以内 | なし | なし |
| 最低宿泊日数 | なし | なし | 2泊3日以上 |
| 住居専用地域での営業 | できる | できない | できる |
| 管理業者への委託 | 規定あり | 規定なし | 規定なし |
| 消防設備 | 原則必要 | 必要 | 必要 |
| 実施エリア | 全国 | 全国 | 特区のみ |
住宅民宿事業法(民泊新法)に関しては、多くの都道府県で「営業できるエリア」などについて自治体が定める条例で規制が上乗せされています。営業する自治体の条例を、合わせて確認しておきましょう。
民泊の始め方について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】民泊の始め方7ステップ!メリット7選・デメリット5選を解説」をあわせてご確認ください。
民泊新法の5つのポイント
民泊新法は、2018年に適正な民泊サービスの提供を目的として施行された法律です。民泊新法を理解するために、以下の5つのポイントについて解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 都道府県への届出が必要
民泊を始める際には、法律に即した設備や運営体制を整えた上で、営業をする都道府県庁に「届出」を行う必要があります。
届出とは必要な書類の提出を指し、行政から「許可」「不許可」の判断を受けることはありません。書類に不備がなければ、都道府県庁に受理されて手続きは完了です。
2. 営業日数は年間180日以内
民泊で安定して収益を上げるには、営業日数が年間180日以内と制限されている点に注意が必要です。180日を超えて営業をする場合は「旅館業法」の許可を得る必要があります。
営業日数が制限されている理由は、民泊が普及することにより、既存のホテルや旅館の営業に不利益になることへの懸念が影響したと言われています。
180日以内の営業日数制限について詳しく知りたい方は、関連記事「【解決】民泊新法180日ルールのポイント3選!利益を上げる方法を解説」をあわせてご確認ください。
3. 住居専用(住専)地域での営業が可能
新法に基づく民泊は、ホテルや旅館では認められていない住宅専用地域での営業が可能です。住宅専用地域は都市計画法で定められており、店舗兼住宅やコンビニなどの小規模店を除き、営業活動が制限されています。
新法による民泊物件は、用途が「住宅」のままで営業できるため、都市計画法による規制を受けません。ただし、多くの自治体では「小中学校の周囲100m以内での営業を制限する」など、別に規制を設けている場合が多いので注意しましょう。
自治体ごとの規制については「民泊の実施制限に関する地方公共団体の条例のとりまとめについて(官公庁)」を参考にしてみてください。
4. 管理業者への委託が必要
民泊新法では、民泊の運営者である「住宅宿泊事業者」は「住宅宿泊管理業者」に管理業務を委託することと定めています。住宅宿泊管理業者とは、民泊施設の管理全般の業務を行う、国土交通省登録の事業者です。
しかし「住宅宿泊事業者」が自ら管理業務を行う場合や、自身が居住している住宅を民泊施設として使用する場合は、住宅宿泊管理業者への委託は不要とされています。
ただし自身が居住している住宅の場合「1日の内で自宅を不在にする時間が原則1時間以内であること」が条件です。
民泊の管理方法について詳しく知りたい方は、関連記事「【初心者必見】民泊の管理方法は2通り!委託が必要なケースと自分で行う方法を紹介」をあわせてご確認ください。
5. 消防設備が必要
民泊で使用する住居は、消防法令上の「特定防火対象物」にあたるため、飲食店やホテルなどと同様の消防設備が必要です。
具体的には「自動火災報知設備」や「誘導灯」などの設置が求められます。詳しくは「用途別設備の一覧 旅館、ホテル、宿泊所等(一般財団法人日本消防設備安全センター)」から確認してみてください。
ただし「宿泊期間中に住宅宿泊事業者が不在にならない旨の届出がある」「宿泊室の床面積の合計が50㎡以下」の場合は「特定防火対象物」に当たりません。
民泊の消防設備について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊の消防法上必要な設備を建物種類別に紹介【費用や手続きを解説】」をあわせてご確認ください。
民泊運営を行う際の問題点5選
民泊運営では法律を守ることはもちろん、経営面や近隣住民との関係など、あらかじめ把握しておくべき問題点があります。ここでは、以下の5つの問題点について解説します。
一つひとつ見ていきましょう。
1. 準備や届出に手間がかかる
民泊の住居の準備や届出書類の作成には、多くの手間と時間が必要です。住居の準備は、台所や浴室などが備えられた居住可能など住宅の準備や、宿泊サービスを提供するための設備を整える必要があります。
また都道府県への届出書類は記入事項が多く、行政手続き等に慣れていない方にとっては時間のかかる作業です。届出書類については「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて(観光庁 民泊制度ポータルサイト)」を参考にしてみてください。
準備や届出の手間を軽減したい場合は、民泊可能物件の仲介業者の利用や、書類作成を行政書士に依頼することを検討してみると良いでしょう。
申請業務の行政書士への依頼について詳しく知りたい方は、関連記事「【完全版】行政書士に代行依頼できる3つの民泊申請業務!費用や手続きを解説」をあわせてご確認ください。
2. 民泊運用できる物件に制限がある
民泊で使用できる物件には条件があるため、どのような住宅でも活用できるわけではありません。民泊施設として活用できる物件は、以下の3つの中でいずれかの条件に当てはまる住宅に限られます。
民泊利用を目的に新築した住宅は、使用できないことになっています。また条件を満たしていることに加えて、住宅には「台所・トイレ・浴室・洗面設備」や「特定防火対象物として条件に合った消防設備」が必要です。
浴室は、浴槽がないシャワーのみの設備でも構いません。条件を満たした住宅を所有していない場合は、自身で物件を探すか、民泊可能物件の仲介業者を活用すると良いでしょう。
3. 安定して利益を上げることが難しい
民泊新法では、営業日数が180日以内と制限されているため、安定して利益を上げ続けることは簡単ではありません。
民泊をはじめるにあたって、物件の調達や設備投資に多額の費用が必要だった場合、短期間では採算が取れない恐れがあります。また、民泊運営を管理業者に委託する場合、利益が減ることを考慮する必要があるでしょう。
民泊で大きな利益を上げるには、初期投資やランニングコストが抑えられ、集客がしやすい物件を選ぶことが必要です。
自身の所有物件がある場合でも、古い建物の場合、設備投資で多額の費用が必要な場合があります。あらかじめ採算の見通しを立てた上で、事業をスタートすることをおすすめします。
民泊運営の費用について詳しく知りたい方は、関連記事「【保存版】民泊運営にかかる9つの費用!始め方を5ステップで解説」をあわせてご確認ください。
4. 近隣住民とのトラブルが起こりやすい
民泊の問題点として、たびたび近隣住民とトラブルが報道などで取り上げられます。具体的には、以下のようなトラブルが挙げられます。
民泊新法では、周辺地域への悪影響の防止として騒音やごみの処理などについて、運営者から宿泊者に説明する義務があると定められています。つまり宿泊者が近隣住民に迷惑をかけた責任は、民泊運営者にあります。
民泊運営者として、事業を始める前の近隣住民への周知や、宿泊者へ禁止事項の説明を徹底することが重要です。
民泊運営のトラブルについて詳しく知りたい方は、関連記事「【これで解決】民泊のトラブル事例5選と3つの対策【相談先も3つ紹介】」をあわせてご確認ください。
5. 建物や備品が破損する恐れがある
民泊は、ホテルや旅館とは異なり、運営者が宿泊施設に常駐していないケースが多いため、設備の破損や備品の紛失などのトラブル発生リスクが高くなります。
例えば外国人宿泊客の場合、悪意がなくてもトイレやお風呂などの使用方法がわからず、破損させてしまうケースは少なくありません。
宿泊施設内の設備の使用方法やルールについては、多言語で説明書を壁に貼っておくなどの対応が求められます。
民泊に向いている物件の特徴3選
民泊を事業として成功させるためには、物件選びが大切です。物件によっては、多額の初期投資が必要であったり、集客が困難である可能性があるためです。ここでは、民泊に向いている物件の特徴について解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 多額の改修費用がかからない
民泊で利益を得るためには、改修費用が抑えられる新しい物件が適しています。水回りなどの改修が必要な場合は、100万円以上の費用がかかる場合があります。
古い物件の場合、水回りだけでなく、汚れや気密性などに問題がある場合が少なくありません。近年の民泊物件は、きれいで新しい部屋が数多く提供されています。法令に沿った設備を整えるだけではなく、集客面からも古い物件の場合はある程度の改修が必要です。
多額の改修費用をかけてしまうと、初期投資を回収するまでの期間が長期化してしまいます。早期に黒字化するためには、改修費用がかからない物件を選ぶと良いでしょう。
2. 利便性が良い
駅やお店などが近い物件は、民泊に向いています。また、民泊の宿泊客は外国人旅行者が多いため、公共交通機関などの利便性が良い物件が好まれます。
民泊物件は、約3万件(令和4年10月12日時点)と全国で数多くあり、集客面で優位に立つためには、利便性は欠かせない要素です。
3. 観光需要がある
民泊物件は、観光需要のある地域にある住宅が向いています。観光庁が発表したデータによると、民泊利用者は、観光・レジャー目的の方が多いことがわかっています。
観光需要が高い地域の物件は集客力が高く、数日の連泊など効率よく利用してもらえるケースが多いです。
民泊を始める際には事前に問題点をあらかじめ把握しておきましょう
民泊運営は、空き家や空き部屋などの資産を有効活用できることが大きな利点です。宿泊者の需要の高い物件であることがわかれば、売却で利益を得ることもできます。
ただし、準備や運営をしていく上で、法令の遵守や採算面などから課題は少なくありません。問題点をあらかじめ把握し、事業を始める前に適切な対応をとることが大切です。

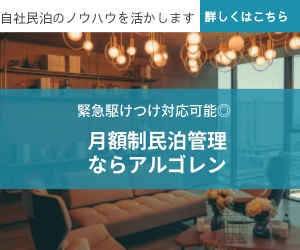








コメント